DX(デジタル・トランスフォーメーション)って最近でこそ耳にするようになりましたが、数年前までは聞いたこともなかった言葉ですよね。初めて聞いた時は私、「DX・・・デラックス?」なんて勘違いしていました。
意味を聞いてからも「デジタル化に取り組むこと?」くらいの、ふんわりした認識しかなかったのですが・・・ある日、テレビで「2025年の崖」という何やら不穏な響きのある言葉を聞き突如不安に。何でも今DX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組まないと2025年には大変なことになるのだとか。
2025年ってすぐですよね。これは大変!言葉の意味くらいは知っておかないと。それに最近は「これからはDX!」なんて当たり前のように言われていて、その都度ひるんでばかりいられませんから。一念発起して「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」について、詳しく調べてみることにしました。
今回は「DXってデジタル化とどう違うの?」といまいちピンときていないあなたにも、スルッと理解できるようにわかりやすく解説してみました。では早速みていきましょう。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)はずばりどんな意味


最近よく耳にするDX(デジタル・トランスフォーメーション)の意味を簡単に説明すると、次のようになります。
ここで大切なのは、DXは単なる「デジタル化」ではないという点。デジタル化はDXを実現するための手段に過ぎません。DXは企業のビジネスモデルそのものを根底から変革することを言います。
まだ少しわかりにくいですよね。次にDX(デジタル・トランスフォーメーション)の概念について、もう少し詳しくご説明しましょう。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)をもっと詳しく説明


「DXって何だかわかりにくい」、「いろいろ読んでいると、よけい意味がわからなくなってくる」、そんなふうに感じたことはありませんか?その理由はDXには2つの概念があることが原因かもしれません。
2004年にスウェーデンのエリック・ストルターマン氏が初めてDX(デジタル・トランスフォーメーション)を提唱した時の概念。「ITが浸透することにより、人々の生活があらゆる面でより良い方向へ変化する」という意味あいです。
日本では2018年に経済産業省がまとめた「DX(デジタル・トランスフォーメーション)レポート」と「ガイドライン」をきっかけに、DXが広く知られるようになりました。経産省はDXの定義を「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス・ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織・プロセス・企業文化・風土を変革して、競争上の優位性を確立すること」としています。
DXは「この2つが同時に世界で進んでいる」と考えた方がわかりやすいでしょう。


テレビの「ダウンタウンDX」は関係ないのね
日本ではスマホを持っている人が多いので「もう十分デジタル化が進んでいるのでは?」と今さらな感じがしますよね。それなのに今、DX(デジタル・トランスフォーメーション)が話題になっているのはどうしてなのでしょう。
そもそもなぜDX(デジタル・トランスフォーメーション)なのか


そもそもどうして今、DX(デジタル・トランスフォーメーション)なのでしょうか。それは次のような理由から。
- 時代の変化に対応(システムの老朽化、デジタル化、消費者マインドの変化)
- 世界競争力ランキングでの低迷
- 「2025年の崖」問題
では順にみていきましょう。
時代の変化に対応
ではまず1つ目の理由「時代の変化に対応」。今DX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組むべき理由は、次のような時代の変化に対応していく必要があるから。
●システムの老朽化(レガシーシステム)
システムの老朽化については、部署ごとに互換性のない古いシステムを改良しながら使っている会社、まだ多いですよね。システムサポートの終了も迫っています。
●デジタル化による劇的な環境の変化(サービスの多様化)
デジタル化による劇的な環境の変化としては、スマホを持つようになったこと、ネットで買い物を済ませることが多くなったことなどがその代表例でしょう。
●消費者マインドの変化(モノ消費からコト消費へ)
モノ消費からコト消費へ・・・これは、「必要な『モノ』はたいてい揃っていて体験する『コト』にお金を使うことが多くなってきた」ことを指します。カーシェアリングや、音楽のサブスクリプションがその代表例。
日本の世界ランキングは過去最低


日本がDX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組むべき2つ目の理由。それは「ビジネスの効率性」が悪く世界から取り残されつつあるから。「日本はITの先進国」だと思っていたら意外や意外。
最近アメリカや中国に先を越されているな・・・と感じていましたがここまでとは。ちょっと驚きですよね。
時代は大きく変わってきているのに、日本企業の経営体質はほとんど変化していないのがその理由でしょう。
これに警鐘を鳴らしたのが2018年に政府がまとめたDXレポートにある「2025年の崖」。


「崖」って、ちょっと大げさすぎません?
「2025年の崖」とは


日本がDX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組むべき3つ目の理由は「2025年の崖」問題。
そしてこの「2025年の崖」を回避するには「レガシーシステム」の刷新が最重要課題になります。
レガシーシステムとは、老朽化、肥大化・複雑化、ブラックボックス化したシステムのこと。
今日本はこの「2025年の崖」の手前で、踏みとどまるか転げ落ちるかの瀬戸際に立っています。DX実現に向けて今すぐ取り組まないと、日本は世界からどんどん取り残されていくという悲しい現実。


「崖」という表現、ピッタリでした
では、DXを導入するためにはどのようなことに取り組めばいいのでしょうか。次に具体的な事例をご紹介しましょう。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)の事例


DX(デジタル・トランスフォーメーション)の代表事例として、今回は料理の宅配サービス「ウーバーイーツ」を取り上げます。
都会ではもうおなじみの「ウーバーイーツ」は、アプリを使って簡単に加盟店の料理を注文できるシステム。アメリカのウーバー・テクノロジーズが展開するサービスで、今も大きく売り上げを伸ばしています。
今日本の企業がこのようなサービスを生み出すには、ビジネスモデルから変革しないと難しいでしょう。しかし、DXを実現して少し頭をひねればこのような成功も夢ではないはず。


日本発でこんなサービスがどんどん立ち上がれば、今の遅れを取り戻せるかも。
ぜひ、期待したいところです。
DXの事例はこちらにも↓
次にDX(デジタル・トランスフォーメーション)を実現することによる、メリットやデメリットについてご説明します。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)のメリットデメリット
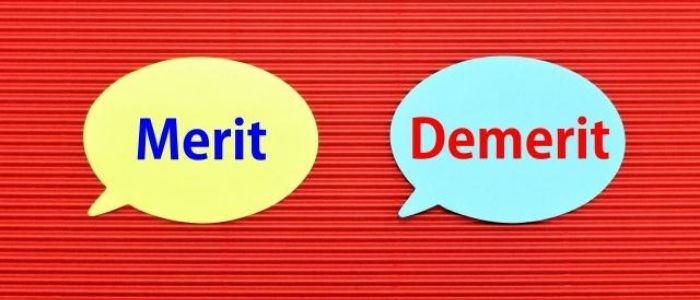
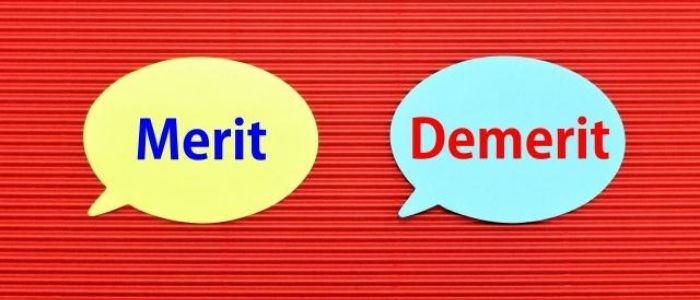
DXによるメリット
ではまず、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を導入した場合のメリットから。
- 効率化が進む
- 生産性が高まる
- 精度の向上
- セキュリティ強化
- 新商品・サービスの開発
- 時代の流れに応じたスピーディーな方針転換
- 新ビジネスの創出
- グローバル展開
最初の5つはレガシーシステム(古いシステム)を刷新することによって、容易に想像できる効果ですよね。
社内共通のシステムを利用することによって他部署の業務も「見える化」し、新たな気づきが新商品や新サービスの開発にもつながります。
後の3つは爆発的に増加するデータを有効利用し、時代の変化に素早く対応していくことにより得られるメリット。DXを実現によることにより、世界に通用する強い企業が生まれてくるでしょう。
DXによるデメリット
次は、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を導入した場合のデメリット。
- 莫大なコストがかかる
- 結果が出るまで時間がかかる
- 方向性を間違うと結果が出ない
- 社内での意識改革が大変
現在、企業のトップはDXの重要性に気づいていても資金面で踏み切れず、目先の売り上げに振り回されているのが実情。
また、実際にDXに取り組んでいる多くの企業も、業績に反映されるまで何年もかかっています。初期費用に加えて、長期的な資金の確保も必要になるでしょう。
失敗例で多いのが、新しいシステムを導入することが目的になってしまってその先の変革をしていないパターン。これはDXではなく単なる「デジタル化」です。
そして案外見落としがちなのが、社内の意識改革。古いシステムを入れ替える際に各部署の連携がスムーズにいかないと、費用をかけた割に結果がでない、ということに。業務プロセスが変わることに反対するケース、よくありますよね。トップの統率力が試されることになるでしょう。
現実問題として、DXに取り組んでいるものの結果が出ていない企業も多くあります。DXは業種によっても取り組み方が違ってくるのが難しいところ。失敗例を共有できればその業界のレベルアップが期待できるのですが・・・。


何とか頑張って欲しい!
では最後に、DX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組んでいくためのポイントをご説明。
これからDX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組むには


DXを導入するにあたって必須になってくるのが「データ活用」です。このわかりやすい例として、2019年に中国武漢で発生した新型コロナの流行状況を表した世界地図があげられます。
その地図は新型コロナ患者の足跡をたどるのに「QR決済」のデータを利用。感染者がどこで「QR決済」をしたか地図上で点と点をつないでいくと、新型コロナの広がり方が一目でわかるのです。
これは目からウロコですよね。ここでのポイントは、病気の広がり方を「医療機関」ではなく「決済機関」が表している点。社内の部署や企業の垣根を越えてデータを活用していくための、お手本とも言える事例でしょう。
世界規模でみると人口はまだまだ増え続け、データは生まれ続けます。そして全てにおいてデータ化は進んでいくため「世界のデータ量」は今後も爆発的に増加していくのは間違いありません。
日本は新しいデータの活用方法を模索していかないと、世界とどんどん差が開いていく一方に。革新的なイノベーションを生み出すには、まず現状を破壊するところから始まります。
そのためには・・・。
- 企業…他部署間での風通りを良くして新しいアイデアを吸い上げる
- 同業他社…同じ仕事をしている者同志で意見交換し、新しい業務形態を模索
- オープンイノベーション…企業・団体などの垣根を乗り越え、全体で進めていく
このような努力が必要となります。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)のもともとの概念は「ITの浸透が社会全体を良くする」というものでした。今の日本は膨大なデータを有効活用し、企業の垣根を越えてDXに取り組んでいくことが重要になるでしょう。


今回はDX(デジタル・トランスフォーメーション)の基本を詳しくお話しました。その内容は、DXは単なるデジタル化ではなく企業や社会を変革するのが目的だということ。また経産省の「2025年の崖」にあるように、今DXに取り組まないととんでもなく大きな損失を抱えることになる、というちょっと怖い話。
その他、事例を交えてDXのメリット・デメリット、これから取り組んでいくために必要なこともお話ししました。
DXは市場の変化に対して柔軟な対応を求められるので、日本の産業構造そのものの変革につながる可能性もあります。そう考えると少し不安になりますが、恐れずに新しい視点を持って取り組めば今までにない新しいサービスや商品が私たちを豊かにしてくれるはず。
今日本に一番必要なのは「危機意識」かもしれません。私たちはDXの取り組み方によって大きく変わってくる未来にもっと目を向けるべきでしょう。
今からITで世界の頂点を目指すのは難しいけれど、スマホの普及率はどこにも負けない日本。ニッチな領域を狙えば世界に通用するサービスの誕生も夢ではないかも。
日本国民が「ダウンタウンDX」の文字を見て、「デジタルトランスフォーメーション」をイメージできるくらいになったら、少しは変わってくるかもしれません(笑)



